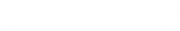3つの「筋収縮」を理解して効率よく筋力向上を目指そう

筋力アップに欠かせない「筋収縮」には3つの種類があるのをご存じですか?この記事では、筋肉が収縮する仕組みとその種類をわかりやすく解説し、トレーニングにどう活かせばよいのかを具体的に紹介します。
筋トレや運動をしているとよく耳にする「筋収縮」という言葉。なんとなく「筋肉が動いていること」と思っていても、実はこの筋収縮には3つの種類があり、それぞれ異なる働きをしています。これらを理解することで、筋トレの効率をグッと高めることができるんです。
この記事では、筋肉が収縮する仕組みや、3種類の筋収縮の特徴、そしてそれらを日々のトレーニングにどう活かすかまで、わかりやすく解説していきます。
筋肉が収縮する仕組みとは?

トレーニングや日常動作の中で、私たちは無意識に筋肉を使って体を動かしています。では、その「筋肉が縮む(=収縮する)」という現象は、体の中でどのように起きているのでしょうか?
ここでは、筋肉の構造や、収縮が起こるメカニズムをやさしく解説していきます。
筋肉の構造について
筋肉(=骨格筋)は身体の骨や関節を固定したり、動かしたりするために必要な力を生み出してくれます。
筋肉は、小さな束が何重にも重なってできています。まず、筋肉全体は「筋束(きんそく)」という束の集まりでできており、その筋束の中には「筋線維(きんせんい)」という細長い筋肉の細胞が含まれています。
さらに、この筋線維の中には「筋原線維(きんげんせんい)」と呼ばれるタンパク質の束がぎっしりと詰まっています。
筋肉が収縮する仕組み
筋肉を収縮させる仕組みは、筋線維の中にある「筋原線維(きんげんせんい)」という構造にあります。筋原線維は「太い線維」と「細い線維」の2種類が、規則正しく交互に並んだ構造をしています。
太い線維は主に「ミオシン」、細い線維は主に「アクチン」というタンパク質で構成されています。筋肉に収縮の指令が届くと、太い線維(ミオシンフィラメント)が細い線維(アクチンフィラメント)をたぐり寄せるように動き、両者がスライドすることで筋原線維全体が短くなります。
この動きによって筋肉が収縮し、私たちは歩いたり、物を持ち上げたりといった動作ができるのです。
「筋収縮」の種類は3つ

筋肉が力を発揮する「筋収縮」には、実は3つのタイプがあります。それぞれに特徴や仕組みがあり、どんな動きでどの筋収縮が起きているのかを知ることで、トレーニングの質もグッとアップします。
ここでは、3つの筋収縮の違いや、具体的な例をわかりやすくご紹介します。
(1) アイソトニクス(isotonics)
日本語では「等張性筋収縮(isotonic contraction)」といいます。なんだか難しそうな名前ですが、実は日常的によく見られる、一般的な動作時の筋収縮がこれにあたります。
日常の動作の中で一定の負荷に対して、動きが伴う筋収縮のことで、
・物を持ち上げたり下ろしたり
・椅子から立ったり座ったり
といった動作がそうです。
アイソトニクスでは、筋肉の長さが縮んだり伸びたりしながら力を発揮します。たとえば、物を持ち上げるとき、筋肉は縮みます。これを「短縮性筋収縮(concentric contraction)」といい、「ポジティブワーク」とも呼ばれます。
逆に、物をゆっくりと下ろすときには、筋肉は伸びながら力を発揮しています。これを「伸張性筋収縮(eccentric contraction)」といい、「ネガティブワーク」ともいいます。
つまり、アイソトニクス(等張性筋収縮)には、
・短縮性筋収縮(ポジティブワーク)※「求心性筋収縮」とも言います
・伸張性筋収縮(ネガティブワーク)※「遠心性筋収縮」とも言います
という2種類がある、というわけです。
そしてこれらの筋収縮の動きを使ったトレーニングをそれぞれ、「ポジティブトレーニング」「ネガティブトレーニング」と呼びます。
例えば『スクワット』であれば、上がる時が「ポジティブトレーニング」で下りる時が「ネガティブトレーニング」にあたります。
(2) アイソメトリクス(isometorics)
日本語では「等尺性筋収縮(isometric contraction)」といいます。「等尺」とは、筋肉の長さを変えずに力を発揮する、という意味です。
たとえば、動かないものを押したり引いたりする運動がこれにあたります。
・壁をグ〜ッと押す
・胸の前で両手を合わせて押し合う
・綱引きでお互いに力をかけ合い、動かない状態を保つ
こうした動きが、アイソメトリクスの代表的な例です。つまり、見た目は動いていないけれど、筋肉にはしっかりと力が入っている状態が「等尺性筋収縮」なのです。
(3) アイソキネティクス(isokinetics)
日本語では「等速性筋収縮(isokinetic contraction)」といいます。これは、動作を一定のスピード(等速)で行う筋収縮のパターンです。
……ちょっとイメージしづらいかもしれませんね。代表的な例としてよく挙げられるのが、水中での運動です。たとえば、水の中で手のひらで水を押して、腕を思いっきり速く動かそうとしてみてください。
加速しようとしても、水の抵抗がブレーキのようにかかって、自然と一定のスピードに保たれますよね。その感覚が、アイソキネティクスです。
スポーツ選手などは、専用のマシンを使って、一定の速度に調節した筋収縮トレーニングを行うこともありますが、一般の人にとっては少し馴染みが薄いかもしれません。
筋収縮の知識を前提にした動作・トレーニングの具体例

筋収縮の種類や仕組みを理解すると、なんとなく行っていたトレーニングが「狙って効かせるトレーニング」へと変わります。筋肉の使い方を意識することで、効率よく筋力を高めたり、ケガのリスクを減らすことにもつながります。
ここでは、筋収縮の知識を実際のトレーニングにどう活かせるのかを見ていきましょう。
筋肉に効かせる意識がフォームを変える
同じ種目でも「どの筋肉を、どの局面で意識するか」によって、トレーニングの効き方は大きく変わります。
たとえばダンベルアームカールでは、ダンベルを持ち上げる際に上腕二頭筋が短縮してポジティブワーク、下ろす際には伸張してネガティブワークが行われています。
体は本来、こうした動きを無意識に調整しながら動いています。
だからこそ、意識を向けることで狙った筋肉に刺激を集めることができるのです。特に「下ろす動作(ネガティブ)」はつい重力に任せがちですが、筋肉にブレーキをかけながら丁寧に戻すことで、より深い刺激が得られます。
トレーニング中は「いまこの筋肉は縮んでいるか?伸びているか?」と、自分の感覚に集中してみてください。こうした意識の積み重ねが、「なんとなく動かす」トレーニングから「狙って効かせる」トレーニングへと変えてくれます。
実際のスポーツや運動、日常の動きの具体例
筋トレ中に使われる筋収縮の種類(アイソトニクス/アイソメトリクス/アイソキネティクス)や、ポジティブワーク・ネガティブワークは、実は日常の運動やスポーツ動作にも深く関わっています。
ここでは、いくつかのスポーツや日常動作を例に挙げながら、それぞれの筋収縮がどのように現れるのかをご紹介します。
階段の上り下り
私たちの日常の動作の中では、無意識的に等張性筋収縮(アイソトニクス)の動作をしていることが多いです。
例えば、階段を上る時は大腿四頭筋(腿の前の筋肉)のポジティブワーク、下りるときはネガティブワークになります。
ラグビーのスクラム
ラグビーのスクラムでは、選手同士が強く押し合いながら体を支え続けます。このとき、筋肉は力を発揮していますが、関節の角度はほとんど変わりません。つまり、筋肉の長さを変えずに力を出すアイソメトリクス(等尺性筋収縮)が働いている状態です。
アイソメトリクスは「止まっている動き」の中で、筋肉に強い緊張を持続させる必要があるため、見た目以上に筋力と体幹の安定性が求められます。スクラムはまさにその好例といえるでしょう。
水泳
水泳では、水中で関節が動く速度に対して筋肉が一定の力を出し続けるという特性があります。これは、アイソキネティクス(等速性筋収縮)に近い状態といえます。
実際には、完全なアイソキネティクスは特別な機械を使わないと難しいのですが、水泳のように常に一定の抵抗とスピードで動き続ける競技では、類似の筋肉の使われ方をしています。
【まとめ】「筋収縮」の仕組みを有効的に使おう!

筋肉がどのように動き、力を発揮しているのかを理解することは、トレーニングの質を高める第一歩です。今回ご紹介した3つの筋収縮の特徴を知っておけば、目的やシーンに合わせたトレーニングがしやすくなります。
無理なく、効率よく身体を鍛えていくために、ぜひ日々の運動にこの知識を役立てていきましょう。
筆者プロフィール
大塚聡 / パーソナルトレーナー(株式会社サミープロジェクト)
株式会社 サミープロジェクト代表取締役
サミーコンディショニングスクール代表
一般社団法人日本生活体力推進協会代表理事
1961 年5 月生まれ
早稲田大学教育学部体育学専修卒
早稲田大学大学院人間科学研究科修了(体力科学専攻)
フィットネスクラブ指導責任者、経営責任者を経て独立
株式会社サミープロジェクトを設立し現在に至る
資格
人間科学(健康科学)修士
教育学士
NSCA-CPT(パーソナルトレーナー)
CSCS(ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)
日本体力医学会健康科学アドバイザー
厚生労働省ヘルスケアトレーナー
中学・高校保健体育教員ら
国際救命救急協会救急心肺蘇生法取得者
主な企業フィットネス実績
・ベネッセコーポレーション高齢者身体づくり教室監修
・日本商工会議所主催生活習慣病予防改善セミナー全国各地にて講演
・モーリスコーポレーション健康事業顧問
・ライオンズクラブ健康セミナー
・公立高校における親子健康セミナー
など、企業の健康関連部門においても多数活動